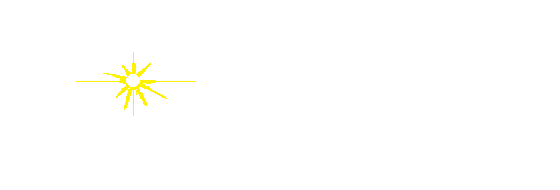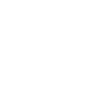連載コーナー

| 新 四 季 雑 感 | (26) |
樫村 慶一
| 日常使う | 日本語には、 | 囲碁・将棋用語が | あふれている |
囲碁・将棋が人気である。室内遊戯の雄であり、上品であり、頭脳強化に有効であり、何よりも面白い。打ちだしたらどちらかが、もう止めよう、と言うまで續く魔性の遊戯である。 世界中に数多(あまた)存在する室内遊戯の中で、「偶然性の介入する余地が最も少ない」あるいは「勝敗にプレイヤーの実力(差)が最も直接的に反映される」競技の一つと言われている。そのため、偶然性が多く入るマージャンは、何かを賭けないと興味が半減なのに対して、囲碁・将棋は実力勝負なので、賭けをしなくても興味は尽きないのである。
関心や関わりのレベルについては、「囲碁も将棋もやらない人」から「プロ並みの実力者」まで幅広いが、その用語や由来・表現の一部が、日本語の中の相当部分を占めていることは、打たない人にはお分かりにならないと思う。その最たる言葉が、「だめ(駄目)」と言う言葉である。殆どの人が一日に一度や二度や、知らない間に使っていると思う。それが囲碁用語であることは、そうか、と言われて気が付く方も多いであろう。そればかりか、日常使う日本語には囲碁・将棋用語がかなり使われているのをご存じない方もおおいのではないだろうか。
それにしても、囲碁と将棋の言葉について、面白い?法則を発見した。軍隊組織に似た名称の駒を使う将棋の言葉には、戦争用語はほとんどないのに、のんびり白と黒の石を並べるだけの囲碁の用語に、残酷な言葉が多いことである。殺す、死ぬ、生きる、生かす、切る、攻める(これは将棋にもある)、囲む、全滅、などなど、すべて囲碁で使われている。
話しを「駄目」に戻して、まず駄目の意味であるが、碁盤には19本の線が縦横にひかれていて、この線が交わったところを「目」と言う。最終的にこの目の数が多い方が勝ちとなる。しかし、数にかぞえられない目がある、駄目は、双方の境界に有ってどちらの陣地にも属さず、石を打っても陣地が増えない場所のこと。つまりやっても意味の無い事、無駄な事である。これを「駄目」といい、日本語の駄目(だめ、だめよ、の駄目)の素になっている。その他で、普通に使われている日本語になっている囲碁・将棋用語の主なものをならべてみよう。
【あ行から~ 】
| あの手この手 | = 次に打つ手が色々あること。 |
| 一目置く/置かれる | = 弱い人が強い人と対局するとき、実力差を縮めるため最初に余計に石をおく、弱い方が先に実力差に従って、決められた数の石を置いて勝負を始めること。つまり自分より相手の方が優れている事を認めて敬意を表し、一歩譲ることを言う。 |
| 上手(うわて) | = 自分より強い人。 |
| 王手(おうて) | = 攻める方は王様をとるぞと言う絶対の手。攻められる方は絶対絶命の場。 |
| 岡目八目(おかめはちもく) | = 時代劇に出て来る言葉で「岡」を使った言葉が結構ある。「岡場所」「岡っ引き」「岡惚れ」等である。岡目八目の「岡」もこれらと同じ意味で、周りより小高い所と言う意味から、傍らという意味が有り、観戦者が上からみると、戦況がよくみえる。このため戦局が客観的に捉えられ、先が的確に読めるので、観戦者が対局者より八目置かせたくらいの上段(実力)者にみえること。 |
| 決め手 | = 勝敗を決する手。 |
| 局面 | = 現在の状況。局とは囲碁や将棋等の勝負のことで、現在の勝敗の行方がどうなっているかといった情勢のことを言う。 |
| 禁じ手 | = 差してはいけない手 *相撲と共通。 |
| 玄人(くろうと)⇔素人(しろうと) | = 囲碁が日本に伝来したばかりの頃は、実力上位者が黒石を使い、下位者が白を使って事からくろうと、しろうとと言う言葉ができた。現在は黒石が下位者で先手。 |
| 結局 | = 手合わせの (勝負)の結末。 結・・・しめくくり。局・・・勝負。 |
| 後手後手/後手に回る | = 防戦におわれ不利になる。 |
| 駒が揃う | = 将棋用語で、攻めるのに都合いい駒が集まったこと。 |
| 駒不足 | = 上記の逆。 |
| 駒を進める | = 攻める。 |
| 下手 | = へた、したで、しもてともいう、自分より実力が下の人。 |
| 上手 | = じょうず、自分より強い人、江戸時代における囲碁七段の別称 |
| 初手 | = しょて、勝負開始直後の手。 |
| 先手 | = 攻めるのに有利な手を持つこと、相手は絶対に守らないといけない。 |
| 定石 | = じょうせき、定石通りに。慣例通りに、過去の歴史で決まった常識的な手。昔からの研究により最善の形とされる、決まった石の打ち方。何かをする時の最善策 とか決まったやり方という意味で使われる。 |
| 将棋倒し | = 読んで字の如し。ドミノ倒しのようなこと。 |
| 白黒つける | = 争いの決着をつける。どっちが正しいか、裁判で白黒を付けよう等の様に言う。 |
| 序盤 | = 序、物事の始まり、盤、囲碁や将棋の台のこと。 |
| 捨て石 | = 他に有利な手を打つために犠牲になる石。 |
| 捨て駒 | = 上記と同じ、将棋用語 |
| 死活 | = 生きるか死ぬか、囲碁では目が二つできる(生きる)か、できないか(死ぬこと)の分かれ目の状態。 |
|
大局観(たいきょくかん) |
= 敵味方、盤全体の情勢。局面、つまり勝負の行方を大きく、全体的に観る能力の事。 |
| 打開 | = 将棋用語として一般化した。「局面を打開する」と使われる例が多い。 |
| 高飛車 | = 将棋の飛車が飛び出して敵陣の目の前にいること。 |
| 段違い | = 柔道、剣道、弓道など段をつかう競技はいろいろあるが、段位の始まりは江戸時代前半期の碁だと言われている。実力の違い。 |
| 手合い/手合わせ | = 対局 相撲語源説あり。 |
| 手薄 | = 守るのに不十分な態勢。 |
| 手加減する、手堅い、手順 | = 手がつく言葉は囲碁将棋から来たものが多い。 |
| 手駒 | = 手持ちの駒。転じて、すぐに動ける手下や部下の事。 |
| 手ずまり | = 戦線が膠着状態になり打つ手がないこと。 |
| 手抜き/手を抜く | = 囲碁用語、優劣が明らかな領域に必要以上の石を使わないこと。 |
| 手を入れる/手を打つ | = 安全を確保するため補強する。 |
| 手を緩める | = 相手は確実に死ぬと分かったので攻撃の手を抜く。 |
| 手を読む | = 自分のこれからの攻め手を考える、相手の出方を想定する。 |
| 駄目押し | = 終局後、互いが念のため双方の境界に石を埋め合って勝敗を確認することで、既に十分なのにさらに念押しすると言う意味となった。 |
| 投げる | = 敗北の宣言、「投了(とうりょう)」と言う。実際に石を盤上に数個パラパラと置いたり、将棋駒を投げ出したりする。 |
| 成り/成る | = 将棋用語、王様と金以外の駒は敵陣の3段目までに入ると「成る」ことができる、”なる”と行動範囲が広がり力強くなる。 |
| ハメる/ハメ手 | = ルール違反ではないが汚い手、わなの様な手。囲碁将棋言葉が一般化したと考えらている。 |
| 布石(ふせき) | = 陣地を展開する。予め敵の出方を想定して手を打っておく。 |
| 目論む/目論見/目算 | = 攻め方を考える、見方の領域を想定する。一般的な意味は確定要素 と不確定要素を計算して総合的に判断した戦略の事。 |
| 持ち駒 | = 将棋言葉 敵から奪った駒。 |
| 八百長(やおちょう) | = 囲碁愛好家で相撲部屋と取引があった「八百屋の長兵衛」の短縮形で、相撲用語の隠語として流通、他の競技全般に派生。 |
| 読み | = これから打つ手に相手が受けて、その先どう展開するかを想定する。先を読む。 |
*まだまだあるかもしれないが、このへんで。
以上が囲碁や将棋の用語に由来する、主な日常言葉である。以上の他に、「隅に置けない」、「手遅れ」、「手落ち」、など「手」のつく言葉の多くも囲碁・将棋用語から派生したと考えられている。囲碁・将棋用語は日本語への浸透度や出現頻度が高く、その他の仏教用語、歌舞伎用語、相撲用語などと並んで、日常会話の中枢をなしている。また競技の性格上、戦略、攻守、手順、状況把握などに関する表現が多い。これだけ見てくると、そもそも囲碁っていつから日本に存在するのか気になる。そこで囲碁の歴史を簡単に見ておこう。
| 636年 | ・隋の書物である「倭国伝」に日本人が囲碁を好むと記載されている。 |
| 701年 |
|
| ・大宝律令に囲碁に関する記載有り。 ・聖武天皇(701-756)の遺品(碁盤や碁石)が正倉院に収められている。 |
|
| 1199年 | ・玄尊(げんそん)が「囲碁式(いごしき)」を作成。 |
| 1585年 | ・秀吉が日海(棋士)を招いて御前試合開催 |
| 1587年 | ・日海は駿河に入り徳川家康と碁を打った記録が有る。 |
| 1612年 | ・幕府は本因坊算砂(日海)等に俸禄を与えプロ棋士が誕生。 |
| 1626年 | ・御城碁(おしろご)が始まり、以後幕府の保護下で盛んになる。 |
古い時代の主な流れは上記の様なものである。中国の歴史書によると、日本では奈良時代よりも前から囲碁を楽しんでいたことになる。 おわり
(2024.10.5記)
「参考資料」
①ウィキペディア 囲碁用語、将棋用語
| wikipedia | https://ja.wikipedia.org |
②インターネットで検索した次のサイト
| Isajiのお役立ち情報館 | https://jouhou-kan.net/ |
| 囲碁関係 | https://jouhou-kan.net/archives/985 |
| 将棋関係 | https://jouhou-kan.net/archives/1088 |
【運営者情報:Isajiです。アラフィフおやじです。医療関係の仕事をしております。医療系、介護関係の資格所有してます。マジックノウハウコレクターです。】
いいね!ボタン
メッセージもよろしく
樫村さんへのメッセージ
樫村さんへメッセージを送りましょう。
新連載について、投稿者の樫村さんへメッセージを送りましょう。
「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)
メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。
ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。
年号早見
☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。