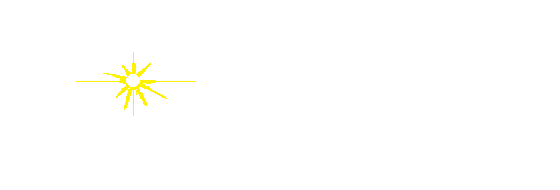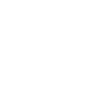トップインデックス
第35回
いいね!ボタン
島崎さんへのメッセージ
坂口さまへ いつもありがとうございます。
坂口さま
いつもありがとうございます!
美術館めぐりは本当に魅力にあふれていますね。
次回はこれをご紹介しようかしら、といつも胸ときめかせているんですよ。
関連本も読みたいですし、目まぐるしくて、いつもうれしい悲鳴を挙げております(笑)
ひきつづきよろしくお願いいたします。
島崎 陽子
島崎さんこんにちは!
島崎さんこんにちは。
k-unetの坂口です。
今回の英-蝶展拝見しました。浮世絵いいでね。勉強になります。
島崎さんの美術散歩は2020年から始められたのですね。
素晴らしいです。
これからも2か月後の作品を
楽しみにしています。
寒くなりましたので気をつけて下さいね。
まちだよもよろしくお願いします。
スマホからのですので上手く書けませんがごめんなさい。
「美術散歩」の著者、島崎さんへメッセージを送りましょう。
「美術散歩」の著者、島崎さんへのメッセージを書き込むことができる欄を設けました。
「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)
メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。
ログインせずに上の❤ハートマークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

年号早見
☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。